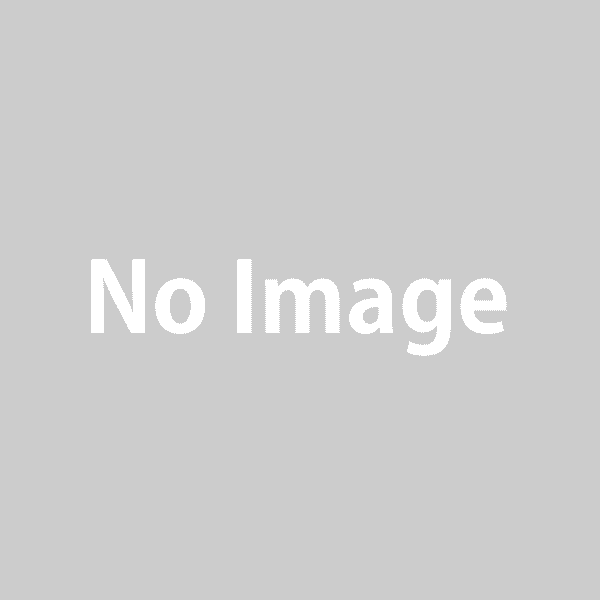内定も期待できる
企業による違いはありますが、就活における試験は面接が主となります。
中には筆記試験を行う事もあります。
大抵は応募人数が多数の場合は、書類選考を行い、書類選考に通過しないと面接すらしてもらえませんが、面接で手応えがあると内定も期待できます。
最近は採用試験に小論文を指定する企業が増えています。
なぜ就活に小論文なのか
なぜ就活なのに小論文を提出しなければいけないのでしょうか。
職種にもよりますが、実際のところはいごとをするために、学校の勉強で学んだ事はあまり役に立ちません。
もちろん中には学校で学んだ事が役に立つ場合もありますが、就活での試験は学力や勉強力よりも、人間性を重視します。
出題された問題に答える事で、学力や勉強力は証明できますが、企業が知りたいのは人間性ですから、それを判断するために小論文を書かせるのです。
小論文でもある程度のボリュームはありますから、きちんとテーマを決め、起承転結に当てはめて書き進めていくので、文章の構成力や理解力、自分の意見をきちんと主張しているかなど、見極めポイントがたくさんあります。
もちろんただ書くだけではなく、読み手の立場に立って読みやすく書いているかもチェックされます。
小論文のコツ
今後も就活で小論文を試験に取り入れる企業は増えていくと言われていますので、小論文のコツを押さえておきましょう。
テーマは基本自由ですが、決まっている場合はそれに従います。
最初は問題提起をして疑問などをはっきりさせておきます。
問題提起の次は、自分と反対の意見を持つ人への対応を盛り込みます。
反対意見がある事を理解しつつ、次に自分の意見を明確に述べます。
自分の意見を押し付けるのではなく、なぜこう思うのか、なぜこういう風に考えたのかという理由を説明します。
最後に総まとめとして、結論を出しますが、この時もう一度自分の意見をはっきりとアピールしておきます。
大体このような構成で進めていくと、小論文が苦手な人でも上手く書けるようになると思います。
テーマが指定される事も多いので、過去の傾向から出題される可能性が高いと思われるテーマをいくつか紹介しておきます。
志望理由は就活においてとても重要とされますが、志望理由に絡めて入社したら何をしたいか、5年後10年後の自分がどうなっているか、どう有りたいかを、テーマに指定する事はよくあります。
志望動機の次に重要となる、自己PRを小論文で伝える事もできます。
学生時代に頑張った事、苦労した事、苦労をどう乗り越え解決したのか、これもよくテーマにされます。
後は時事問題もよくテーマに指定されますので、時事問題に関する情報やニュースはこまめにチェックしておくクセを作るのも良い方法です。