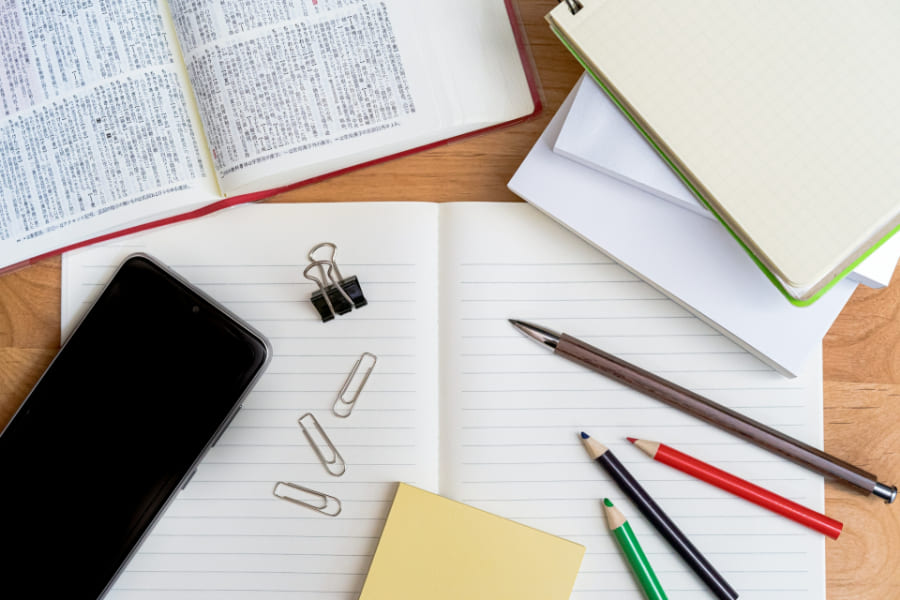
公務員の種類、その試験概要、基本事項を理解しよう
不況が継続し現代の学生は親の苦労をそばで見てきたという事もあり、将来は不安定要素が多い民間企業よりも、公務員という安定の道を選択しようという方が多くなっています。
超大手企業も倒産する、経営危機になる、合併となった・・・等のニュースが毎日流れる中で成長してきた現代の学生は、儲かる、儲からないという事以前に、安定しているかどうかをよりよく考慮して就職先を探すようになったのです。
この先、公務員を目指す方は、まず公務員の種類を理解しておくことが求められます。
かなり多くの種類がありますので一部、紹介しておきます。
公務員の種類は数多い
公務員というと役場の職員や学校の先生、それに警察官や消防などを思い浮かべる方が多いと思いますが、実際にはすべて合わせると50種類という数の職種があるといわれています。
公務員は国家公務員と地方公務員に分けることができ、その中から法律系や経済系、公安系などに分類する事ができます。
例えば航空管制官も公務員です。
飛行機の離着陸、運行状況をチェックする仕事で、ここで働く人たちは航空会社の方ではなく公務員です。
自衛官、こちらも公務員です。
災害の際など、指令を受けて勤務する事が多く、私たちにとって非常に頼りになる存在です。
有事には国益を守るために力を発揮します。
税務署で国税について関わる税務職員も公務員です。
国家公務員の中でも税務についての専門職となり、確定申告に関わるのもこの税務職員ですし、財産などに関わる税金など、税金に関するプロとなる税務職員も公務員として働いています。
知りたい!!公務員試験の概要
将来安定した仕事に就きたいから公務員になりたいという方、消防や警察官、また自衛官に憧れて公務員を目指すという方、それぞれ理由はあると思いますが、公務員になるためには試験を受ける事が必要です。
試験は、教養試験、専門試験、論文試験、人物面接など、受ける公務員の種類にもよりますが、一般的にこのよう餡試験となります。
教養試験では法律や経済、時事等の幅広い教養が求められますし、専門試験では公務員の種類によってかなり難しい法律や憲法について学ぶなど、様々なことがあります。
何れも、幅広い知識と目指す公務員の種類によって専門的な勉強も必要となります。
年齢ですが、就職してからやっぱり公務員を目指したいと27歳くらいから公務員を目指したという方もいます。
年齢的なものはそれほど関係ないといわれます。
公務員の職種によっては応募年齢が決まっている事もあります。
公務員になるためにはどのような勉強が必要となるのかよく理解し、また職種によってはこの学校に行っていないとなる事が出来ないという事もあるので、しっかり確認する事が求められます。







